[1973年 – 1974年]
アフリカ東部編 17 チャナカレ[トルコ] → カイロ[エジプト]
トロイの遺跡
チャナカレの町を歩きまわったあと、南へ。町外れまで出たところで、バスが停まってくれた。運転手は「どこに行くんだ」といってるようだった。「トロイ!」と叫ぶと、「こっちへこい」と手招きしている。またしてもバスにタダで乗せてもらう。ドイツ人のシュリーマンが生涯をかけて発掘したトロイの遺跡に寄ってみたかったのだ。
トロイはイズミールに通じる幹線道路から5キロほど入ったところにある。バスの運転手はトロイへの入口で下ろしてくれた。トロイまで歩き、入場料の5リラ(約100円)を払ってトロイの遺跡を見てまわった。
遺跡自体はそれほど大きなものではない。説明してもらはないことには、どれが何なのか、よくわからなかった。しかし、世界史の時間にならった歴史の舞台に今、自分の足で立っているという、その満足感だけでもう十分なように思えた。
トロイからまた5キロほどの道のりを歩いて戻ると、幹線道路沿いの村からは陽気な音楽が流れてきた。旅芸人の一座が民家の庭先で太鼓をたたき、笛を吹き、バイオリンをひき、それに合わせて村人たちが踊っていた。ぼくの姿をみつけると、その家の主人は珍しい客がやってきたといわんばかりに隣の席をあけ、酒をつぐ。遠慮なく飲み干すとさらにつがれ、酒のあとは料理までふるまわれた。
旅芸人の一連の演奏が終わり、村人たちの踊りも終わったところで立ち上がったが、けっこう飲んだようで足元がふらついた。家の主人や村人たちと握手して別れ、幹線道路を南へ、イズミールを目指して歩いた。なんとも忘れられない「トロイ」になった。


地中海の春風
トロイからイズミールまでは300キロほどあった。トルコもヒッチハイクの楽な国ではないが、なんともラッキーなことに、その村外れで一発でイズミールまで行く車に乗せてもらった。エーゲ海沿いの道を車は100キロ以上の猛スピードで突っ走り、イズミール湾の一番奥にあるトルコ第3の都市イズミールにあっというまに着いた。
イズミールの町を歩いたあと、郊外までは列車に乗った。わずかな距離だったが、鉄道も大好きなぼくなので、ものすごくいい旅のアクセントになった。
エフェソスの遺跡に立ち寄ったあと、海岸地帯から内陸地帯へと入っていく。アイディーンからデニズリへ。アナトリア高原の山々にはまだ雪がかなり残っていた。タウルス山脈を縫う険しい山道を通って地中海のアンタリアの町に下っていくと、そこにはもう、北の寒さはなかった。頬をなぜる風が日本の春風を思わせ、なんともホンワカとした暖かな気分になるのだった。
アンタリアからは地中海に沿って東へ。切り立った断崖がストンと海に落ちている。道はといえば、そんな断崖の中腹を通っている。はるか下の方に地中海を見下ろす。背筋がスーッと冷たくなるような険しい道がつづいた。そんな断崖地帯を走り抜けると広々とした平野に出て、メルシーンの町に着いた。
メルシーンからはアダナ、ガジアンテップを通り、シリア国境へと向かう。いよいよトルコも最後になった。






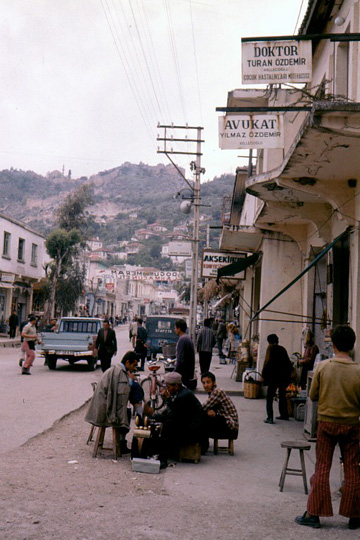


トルコという国
トルコでのヒッチハイクは楽ではなかった。ぼくが歩いていると、いたるところで人々は群がるようにしてやってきた。体をさわったり、勝手にザックをあけて中を見られたこともある。トルコ語がカタコトしかわからないのに、次から次ぎへとペラペラまくしたてられる。そのあげくに、きまって
「トルコはいい国だろ。世界中でトルコほどいい国はないだろ」と、半ば強制的に同意させられる。
「どこから来たんだ? 中国か、ベトナムか?」
「おー、そうか、おまえは日本人か。それだったらカラテを知っているだろ。教えてくれ。でも、日本人には悪いヤツが多いからな」
トルコでは中国製のカラテ映画が大はやりだった。そのたぐいの映画の大半は日本軍が中国大陸に侵攻した当時の時代背景。日本人は徹底的に悪役で、善玉の中国人が空手で悪役の日本人をやっつけるというストーリー。観客は悪役の日本人が善玉の中国人にやられるたびに声を上げて喜ぶのだ。
「日本人には悪いヤツが多いからな」は、そんな中国のカラテ映画から来ている。
あまりにもヒッチハイクができないので、バスに乗ったこともある。トルコではバス交通が発達している。長距離でも鉄道ではなく、バスを使うことが多い。長距離バスは便数も多く、快適で速い。そんなバスなのだが、大きな町のバスターミナルでは大変な目にあう。大勢の客引きが待ち構えているのだ。彼らはぼくの腕をつかみ、まるで大根でも引き抜くように、力いっぱいつかんだ腕を引っ張っていく。もう「やめてくれ」と叫びたくなる。
バスに乗ると、車内では乗客たちのなめまわすような視線を浴びる。やたらとコンコンと咳き込んでいる人が多い。トルコ人ほどタバコをよく吸う民族もいないのではないか…と思うほどよく吸う。咳き込んでいるのはきっとそのせいだろう。そして必ずといっていいほど、誰かが「1本、吸わないか」といって持ってくる。「ぼくはタバコを吸わないんですよ」といってもわかってもらえない。「どうして俺のタバコを吸えないんだ」と怒ったような口調になる。ヒッチハイクも大変だが、バスに乗るのも大変だった。
しかし、見方を変えれば、トルコという国、トルコ人という民族はそれだけ土着性が強いということになるのだろう。ヨーロッパと地続きだとはいっても、ヨーロッパとは違うトルコ独自のものをしっかりと根づかせている。
ヨーロッパを中心にして見てみると、おもしろいことに気がつく。
「ピレネーを越えればもうアフリカ」ともいわれるように、スペインという国は同じヨーロッパとはいっても西欧とは大きく異なる。同じようにユーゴスラビアやブルガリアもそういう意味ではスペインに似ている。さらにスペインの南、ジブラルタル海峡を越えたモロッコになると、アラブ世界へと世界は大きく変わる。ボスポラス海峡もしくはダーダネルス海峡を越えたトルコはモロッコとじつによく似ているように感じられるのだ。
2つの国の大きな違い
ガジアンテップから国境近くの町キリスまではバスに乗った。そこから国境までは10キロほど。町の人の話では夕方の5時になると国境事務所は閉まってしまうという。なんとしてもそれまでには着こうと、懸命になって早歩きした。幸いなことに、税関の車が通りかかり乗せてくれた。途中には軍の検問所があり、何ヵ所かには見張り塔が立っている。道の両側にはバリケードが張られている。シリアとの国境なのに、どうしてこれほど厳重に警備する必要があるのだろうかとちょっと不思議な気がした。
税関の係官のおかげで5時よりもはるか前に国境に到着。トルコ側の出国手続きは簡単に終わり、シリア側に向かう。道沿いには有刺鉄線が何重にも張られている。そんな道を歩いていくと、機関銃を構えた兵士の立つ監視塔があり、そこを過ぎたところがシリア側の国境事務所だった。シリア側の入国手続きも簡単に終わった。
シリア側はトルコ側とは違って、なんとものんびりとした風景。バリケードや監視塔、軍人のたぐいは一切消え去った。小麦畑では農夫がもくもくと畑を耕し、春の野花が咲き乱れる草原では羊が群れている。オリーブ林も見られる。2つの国のあまりの違いに驚かされてしまうのだった。
貧乏旅行の辛さ…
シリアに入り、ヒッチハイクでシリア北部の中心地、アレッポへ。商店で残っていたトルコリラをシリアポンドに替えてもらった。85リラが20ポンド40ピアストルになった。アレッポから首都ダマスカスまではバスに乗った。ホムスを通り、古くからオリエントとヨーロッパを結ぶ十字路として栄えてきたダマスカスには夜、遅くなってから到着した。固くなったパンをかじり、タマネギを生でかじり、その夜はダマスカスのバスターミナルでゴロ寝した。
翌朝、ダマスカス駅に行く。列車でヨルダンのアンマンまで行き、さらにアカバまで足を延ばし、そこからダマスカスに戻ってくるつもりにしていた。しかし、その日のアンマン行きの列車はなかった。そこでバスターミナルに戻り、バスでアンマンに行こうと思った。ところがアンマン行きのバスもかなり待たなくてはならなかった。ちょうどそこにいたアンマンまで行くというトルコ人と「タクシーで行こう」ということになり、乗合タクシーの乗り場に行った。しかし1人10ポンド(約830円)だといわれ、乗合タクシーを諦め、ダマスカスの南のデラまで行き、ヒッチハイクしようとした。
シリアでのヒッチハイクもきわめて難しい。結局、車に乗せてもらえないまま時間だけが過ぎ、ヨルダン行きを諦めた。このあたりがギリギリのお金でできるだけ世界をまわろうという貧乏旅行の一番の辛さ…。
食堂でパンとサラダ、豆のスープの食事をするとダマスカスの中心街に戻り、再度、乗合タクシーの乗り場に行った。今度はレバノンのベイルートまでの料金を聞くと1人7ポンド(約560円)だという。アフリカに早く戻りたいという焦るような気持ちもあって、ベイルートまでは乗合タクシーで行くことにした。




モンゴル系パキスタン人
ベイルート行きのベンツの乗合タクシーにはぼくを含めて5人が乗った。その中の1人はモンゴル系パキスタン人。日本人そっくりな顔をしていて、最初に見たときは、てっきり日本人だと思ったほど。
1971年にはバイクでアラビア半島を横断したが、その時、サウジアラビアでは何度となく、「パキスタニ(パキスタン人)か?」と聞かれた。パキスタン人によく間違われたおかげだと思っているが、このときはなんとバイクでイスラム教の聖地、メッカに入り、カーバ神殿にも入ることができたのだ。ベイルート行きの乗合タクシーの中で日本人そっくりなパキスタン人を見て、「う〜ん、なるほど!」と、サウジアラビアでの「パキスタニ(パキスタン人)か?」が理解できるのだった。
しかし、大多数のパキスタン人はアーリア系民族で日本人にはまったく似ていない。1971年の旅では1ヵ月ほどパキスタンの各地ををまわったが、日本人そっくりなパキスタン人に出会った記憶はない。
大都市ベイルート
ベイルート行きのベンツの乗合タクシーはダマスカスの市街地を抜け出ると高速で走り続け、あっというまに国境に到着する。レバノンとの国境は人でごったがえしていた。「ダマスカス〜ベイルート」間の人の行き来はきわめて多いということがひと目でわかる光景だった。それでも簡単にシリア側の出国手続き、レバノン側の入国手続きは終わり、レバノンに入った。
アンチレバノン山脈の峠を越えると、前方には雪をかぶったレバノン山脈の山々が見えてくる。アンチレバノン山脈とレバノン山脈の間は平地になっている。うっとおしい雨雲が厚く低くたれこめている。いよいよレバノン山脈の峠道に突入。雨が降ってきた。グングンと高度を上げ、雪に手が届きそうなところまで登っていく。空気が薄くなったせいなのか、この峠道の登りでベンツの調子が悪くなり、運転手は2度、3度と車を停めてボンネットを開けた。やっとの思いで峠を越えると、ベンツはもとどおりの調子を取り戻し、一気に峠道を下った。
やがて灰色の靄に包まれたベイルートの市街地と灰色の地中海が見えてきた。ベイルートの市街地に入っていく。さすが中東第一の都市。高層のビルが建ち並んでいる。大通りの渋滞に巻き込まれると、とたんにベンツの乗合タクシーはノロノロ運転になった。ベイルートはダマスカスとは比べものにならないくらいに車が多かった。





ベイルートの休日
乗合タクシーはベイルートの中心地のひとつ、マルティール広場に到着。そこで5人の乗客は降りる。広場のまわりには両替屋が何軒も軒を並べている。これほど両替屋の多い都市は見たことがない。それほどの多さだ。ここで残ったシリア・ポンドをレバノン・ポンドに替えた。
広場のまわりには映画館もあり、その奥は大きなスーク(市場)になっていた。様々な店が狭い場所にひしめきあい、様々な人種の人たちが買い物をしていた。ベイルートは国際都市だ。
ベイルートに着いた日は金曜日。イスラム教国のシリアでは当然のことだが休日だった。ところが国境を越えてレバノンに入ると平日だ。キリスト教徒の多いレバノンの休日は日曜日なのである。
ベイルートには4日、滞在した。「ベイルートの休日」といったところだ。その間、何本もの映画を見た。映画館の入場料は1ポンド(約100円)ぐらい。75ピアストル(約75円)という映画館もあった。この国でも中国(香港)の空手映画が人気だった。そんな空手映画を3本見たが、3本とも日本人が悪役。日本人がいつも悪役というのはほんとうに腹がたつが、それはともかく、とにかく見ていて胸がスカッする。空手を用いての格闘のシーンの連続に観客からはやんやの歓声が上がった。
イスラエル行きのバスの出る日
マルティール広場からはダマスカス、アンマン、バグダッド、イスタンブールへと長距離バスが出ている。さらにはヨーロッパ各国の大都市へも長距離バスが出ている。しかしイスラエルのテルアビブやエルサレム、ハイファ行きのバスは1本もない。すぐ隣の、それも手の届くような近さなのに…。ベイルートにいるとイスラエルは遠い遠い、はるかかなたの国なのだ。
マルティール広場からそんなテルアビブやエルサレム行きのバスの出る日が来ることを願わずにはいられなかった。中東の戦火がやみ、ほんとうの平和がこの地に訪れたとき、ベイルート発テルアビブ行きやベイルート発エルサレム行きのバスが出るようになるのだ。さらにシナイ半島からスエズ運河を渡り、エジプトのアレキサンドリア行きやカイロ行きのバスが出るようになる。そんな日が1日も早くやってきますようにという願いを込めて最後のマルティール広場を歩いた。
アフリカ大陸が見えてくる…
エジプトのカイロに飛ぶ日がやってきた。ベイルートの旅行代理店を何軒もまわり、やっと正規の料金の半額という安いチケットを手に入れた。そして1974年4月8日、カイロを経由するベイルート発ハルツーム行きのスーダン航空機に乗った。機内はガラガラで乗客は数えるほどしかいなかった。
スーダン航空機はベイルートの空港を飛び立つと地中海の上空へ。雲が多かった。しかしエジプトに近づくと雲は切れ、北アフリカの海岸線がはっきりと見えてくる。「ナイルデルタが見られるゾ!」とおおいに期待したが、ナイル川の流れと緑の沃野はいっこうに見えてこない。一面茶褐色の砂漠だけが飛行機の小さな窓から見下ろせた。スーダン航空機はナイルデルタ西側の砂漠地帯の上空を飛んでいるようだった。砂漠には点々とちぎれ雲の影が映っていた。カイロに近づくと、砂漠とナイルデルタの境が1本のはっきりとした線で見られた。その線の内側は一面の濃い緑。その線の外側にはひとかけらの緑もなかった。こうしてカイロの空港に降り立った。またアフリカに戻ってきたのだ。